ホルン練習 自律的思考 10選
Last Updated on 2024年4月13日

大人になって楽器を続けてられる方、ブランクがあって復帰された方へ。
どんな練習をされてますか。どんな考え方で、楽器と向き合っていますか。
シニア前に楽器復帰し、学生の頃と違う様々なことに気付きを得ました。
この記事では、自分自身の経験から、ホルンの練習に対する「自律的思考」を10個紹介します。
ホルン練習 自律的思考 10選
学生の吹部の練習が先生の統治型だとすれば、大人の楽団は自律型です。
学生の方も少子化の影響で教えてくれる先輩がいない方もいるでしょう。
大人の方も教えてくれる人は近くにいなく、個人がそれぞれ独自の考えをもっているのが現状です。
学生以来の数十年間のブランクがある方は、自分にとって「リセット期間である」とポジティブに考える。楽器を吹きたい。どうせ吹くなら、上手になりたいという気持ちや目的がふつふつと湧いてくる。
近道はオンラインやリアルでプロのホルンの先生のレッスンを受けることでしょう。
でも、お金をかけず、まず、まともな音が出せるように考え方を変えてみる。
大人だから、自分の演奏レベルを上げるため、自律的に考えて練習していこう。
ホルンは素晴らしい役割を果たす楽器です
後打ちとは、拍の裏(例えば4/4拍子だと4分音符の裏、つまり8分休符+8分音符)を連続で演奏することです。スーザのマーチ、行進曲などは悲しいほどに後打ちが連発します。
逆にシンフォニックな吹奏楽曲の場合は、非常に重要な役割を果たします。クラシック音楽などを聞くと、ホルンが要所要所で大活躍しています。
これは、吹部に入部した時に練習した楽曲の選曲に問題があったと思います。運が悪かったにすぎなかったのです。
ホルンは素晴らしい役割を果たす楽器です。
金管楽器でありながら、木管楽器のような繊細でやさしい音色を出せる。逆に、たくましい深い音色も出せる。ホルンはいろんな可能性を持った楽器であるということをまず理解しましょう。
教則本は楽しい
部活での練習は「やらされ感」を伴うことがあります。
基礎練習の一環として教則本で練習します。吹部だった頃の教則本は正直退屈でした。何も面白みがありません。これをやって本当に上手くなるのか?
先輩の視線も気にしながら、とにかくつらかった印象しか残ってません。
しかし、大人の今、練習で使っている教則本はとてもやりがいがあって面白いです。
教則本の中の1曲1曲に「何の演奏技術向上を目的に書かれているか」、を想像しながら演奏します。
例えば
- なぜここでこの跳躍なんだ!
- なぜここで臨時記号で半音下がるのか
- なぜこんな複雑なアーティキレーションを用いているのか
- なぜ低音でフォルテ、高音でピアノ。何がしたいのか
- なぜここで前半と微妙に違う音階になっているのか
- なぜ後半に激しい跳躍、音飛びが集中しているのか
などです。
また自分の弱点も見えてきます。
- このパターンの時に音をよく外すな
- あの跳躍をした時の後の音の音程が低すぎるな
- 3番指が不器用だな
- 曲の後半バテ気味でスタッカートが甘くなるな
- 8分音符が続くと後半テンポが甘くなる(はしる)な
などです。
吹部だった頃と違い、自分で自主的に課題を見つけ、自分で考える。そしてそれを修正していくプロセスが面白いのです。
全く「やらされ感」がありません。
ちなみに教則本はKOPPRASCH(コプラッシュ)です。お勧めです。
マウスピースは迷ったらこれ!
ホルンのマウスピースは色々な種類があって迷うものです。私も5本ぐらいもってました。わけもわからず、使い分けたりしていました。
知識がなかったのでしょうか、楽器に相性の悪いタイプのマウスピースも持ってました。私の楽器はホルトンでマウスピースはアメリカンシャンクが適合するのです。しかし、ヨーロピアンシャンクのマウスピースを持って、演奏で使用していました。
今、考えると全く無知でした。
楽器復帰に向けてマウスピースを見直しました。
- 初心者から上級者まで幅広く使われているもの
- ロングセラーなもの
- オーソドックスなもの
私の場合は初心者ではありませんが、ブランクが何十年もあるので初心に戻ったつもりでマウスピースを新調します。
結果、ティルツUカップ8 Sにしました。

楽天URL
https://item.rakuten.co.jp/ontai/1486675/?s-id=ph_pc_itemimage
この新調した1本でまともに演奏できるようになるまで、浮気はしないぞと誓います。自分がたくさん持ってマウスピースは他人に譲るなどして処分をしました。Vカップのマウスピースは1本だけ残しています。
つまり、マウスピースは2本です。 練習でも本番でもティルツUカップ8 Sのマウスピースのみ使用しています。マウスピース選びに時間を使うなら、さっさと練習しようという考えが根底にあります。
自分はどうなりたいんだ?人生論ではありません。吹部の頃は自分がどうなりたいか、どんな奏者になりたいかなんて全く考えていませんでした。
今、この年齢になって楽器復帰、「何のために?」を考えるようになりました。もちろん今からプロになるわけでもなく、趣味の一環として楽しめたらいいかなと思っています。あるいは「ホルンを吹くじじいがあの山にいるぞ」と噂になることでも良いかなと考えます。
練習していると、なかなかうまくいきません。何十年のブランクがここで効いてくるわけです。ここでイライラしてしまっては意味がありません。そこで考えるわけです。
夢でもいい。考えてみるのです。
自分の演奏を誰かに披露できたらいいな。そして、それを聞いてくれた人の心に感動を与えられたら、と考えました。そのためには、楽しく練習を積み重ねて行こうと思うわけです。
好きなように。自分オリジナルの音を目指せばいいんだ!
好きな曲を好きなテンポで、好きな表現で、自分の気に入った音色で演奏すればいいんだ。と、気付いたのは最近です。
吹部の頃はコンクール等あり、「統制」を保つことが求められます。
何らかの団体に所属している場合でも、自由度はある程度制限されると思います。
今、楽器を復帰・再開し、マウスピースも新調し、久しぶりに自分の生音を聞くととても新鮮です。
自分はどういう音を目指すのか。いや目指すというより、どう言う音を出したいのか。この曲のこの部分はこんな表現で、こんなん音色で、こんなテンポで、というふうに考えるようになります。
自分で考えて、好きなようにやればいいんだ。これが楽しいんだ。自分の型はこれから自分で作っていけばいい。トライ&エラーで修正しつつ。とにかく楽器に息を入れ込むのです。
与えられた譜面ではなく、自分で好きな曲を吹くと発見がある
カラオケが楽しいのは自分の好きな曲を思いっきり自由勝手に歌うからでしょう。
歌いたい曲がない時は検索をして、その時の感情で曲選び、上手下手関係なく歌うことでしょう。
たまの息抜きに、ホルンでもやってみたらいかがでしょう。
自分の好きな曲を吹く。吹奏楽曲にこだわらず、ほかの楽器の譜面をもってきてやってみると、とても楽しく、テンションが上がります。
例えば
- 30年前のアイドルの歌謡曲
- 演歌・ジャズ・ラテン
- 合唱部の曲
- 小学校の校歌
- 他の楽器のおいしいメロディーの部分
- 中学生の音楽の歌集やリコーダー(縦笛)の曲
- 甲子園の応援歌
- トランペットのソロ曲集
- 沖縄の楽曲
などです。
いろんな曲を吹くことによる発見もあります。
- バイオリン、ピアノの曲は音の跳躍が激しい!ホルンではついていけない。
- 5線からはみ出した音が読めな。特にフルート。
- ヘ音記号、ハ音記号の楽譜が読めない。
- モーツァルトのホルン協奏曲第一番を吹いてみたら、薬指がつる。
などです。
こだわりを捨てよう。捨てれば気持ちが軽くなる
人生においてもこだわりを捨てれば楽に生きれるといいます。ホルンも同じ。
こだわりを捨てる-その1 どの曲も生読み(inFで)
ほとんどの譜面はピアノ調(inC)で書いてあります。
真面目にやるならば in F に移調して演奏すべきかもしれませんが、正直めんどうくさい。練習することが目的なので、調に関するこだわりを捨てます。
こだわりを捨てる-その2 教則本に書いてある理想的な指導
ほとんどの教則本や入門書の最初のページに
- 理想的な姿勢
- 理想的なマウスピースを唇にあてる位置や角度
- 右手の形や位置
について、書いてありますね。
そして最も重要なアンブッシャーについても細かく、色々書いてあります。読めば読むほど分からなくなります。その通りでやったところで、自分に合う保証はありません。
これは、「ガイドライン」であって、これをベースに自分で合うようにアレンジすればいいのです。
私は猫背です。猫背は「猫背なりのスタイル」があるのではないかと超越的思考になりました。
ともかく、自分の目指す「よい音」が出ればよい。結果オーライの世界なのではないかと思います。
ですので、教則本や入門書に書いてある理想的な指導は参考程度に留めておきましょう。そしてさっさと次のページを開いて練習曲を吹き込んでいくことに注力しましょう。
こだわりを捨てる-その3 細かいことに時間を使わない
ここで言う細かいことというのは
- 練習中のミストーン
- アーティキュレーションの間違い
- 強弱の間違い
を指します。これらを無視していいということではありません。過剰に意識しすぎて停滞してしまい、楽しくなくなってしまうことを危惧しているのです。
練習曲を一度で完璧(ここでは譜面通りに)にできるわけはありません。メトロノームを鳴らしながら、とにかく前に進んでいく。細かいミスに気づいて曲を中断したり、何回もその部分をやり直すことは最初のうちは非効率です。それよりも自分ができなかった部分をチェックする意味で、最後まで通して演奏します。
もちろん何回やっても演奏できてない場合は、テンポを落とすなどして、部分練習するのがいいかもしれません。
ある程度吹けるようになったら細かいミスにはこだわらないことです。最初は30点かもしれません。曲を最初から最後まで通して演奏し切ることに注力しましょう。そう、途中でばてない持続力を作ることです。何回も繰り返しているうちに、ミスを減らし精度を上げていけばよいのです。そうすると、50点になり、70点になり、90点になっていきます。
高音は練習しないといつまでも出ないよ
自分の演奏の中で苦手な部分が誰でもあると思います。
例えば
- タンギングがうまくいかない。
- デクレッシェンドがうまくできない。
- 音程が不安定だ。
- すぐにバテてしまう。
- 高音が苦手だ(低音は苦手だ)。
など、あると思います。
どれにも共通していますが、特に「高音が苦手」はよくある話です。
楽譜の中で高音が出てきたら音が出ないと演奏に穴が開いてしまいます。目立ってしまいます。これは困りました。
結論としては、高音の練習をするしかないです。高音の練習は難しいです。しかもホルンという音を外しやすい楽器で。難しいというか頭を使います。
- ブレス
- アンブッシャー
- アパチュア
- 息のスピード
- 高音のイメージ
など、たくさんの要素があります。
これも最初30点で良いです。30点でも他のせいにしないことです。
例えば
- 体力のせい
- 年齢のせい
- 楽器やマウスピースのせい
- 天気のせい
- 仕事のせい
- 今日の運勢のせい
などです。
淡々と諦めずに練習をすることです。練習といっても特別なことはありません。高音にチャレンジしていく。基礎練習に高音の練習を組み込むだけです。音が出なくても息を入れる。これを毎回行います。ただそれだけです。
思い出してください。初めて楽器を持った時に出た音は何でしたか?。それから1年後どうなりましたか?。音域が広がっているはずです。合奏でよく出てくる音は練習するので、勝手に音域が広がっただけです。
高音の練習ですが、経験上、スラー(長音)よりはタンキング(短音)の方が高音が鳴りやすい気がします。高音域を広げていくイメージで、自分の限界音の3度下あたりから半音階で上げていく練習がいいでしょう。あくまで自分の経験です。
最初は貧弱でカスカスな音色、あるいは音にすらならない、息の音かもしれません。しかし、それを繰り返していくと何ヶ月か後には次第に音になってきます。さらに続けると「芯のある音」になってきます。苦しそうな高音から卒業できます。
諦めない。他のせいにしない。イメージをもって練習あるのみ。
1音1音にツボがある
指に頼った音作り。これは間違っていた。
「ド(F)」から「シ(E)」に半音下がる時、中指を押し下げれば「シ」は発音されます。その時、頭を使っていますでしょうか。指に頼って偶然に半音下がったのではないでしょうか。
「シ」にも「シ」のプライドがあります。つまり1音1音にツボがあるのです。単独で「シ」を吹いてみましょう。次に「ド」から「シ」に下がってみましょう。「シ」は同じ音色でしょうか。
ツボに当たっていれば同じ音色になるはずです。大胆に言えば指に頼らず、全身でツボに向き合いましょう。
究極のフィードバックは自分の音を録音する
自分の音を録音するのはちょっと恥ずかしいです。録音するのはいいが聞くのに若干の勇気がいります。
しかし、アスリートが自分の弱点を見つけるために自分のプレーをビデオに撮って、それを見て研究し改善につなげていくというのと同じです。
「いやいやプロになるわけじゃないので、そこまでしなくてもいい」という方は、この記事は読み飛ばしてください。
私もプロを目指しているわけではありません。お笑いネタとして、記録簿として録音しています。やってみると、すぐになれます。
自分の音を聞くと様々な発見があります。 例えば3年たって、当時の音を聞いた時、変化感じるきっかけになるはず。その感動が、きっと更なるモチベーション向上につながることでしょう。
録音を聴くのが恥ずかしい、聞いたら落ち込みそうなら、今、聞かなくてもいい。とりあえず、将来のために録音しておきましょう。
さらに究極のフィードバックはプロと自分の演奏を波形で比較する
Audacity というソフトウェアがあります。mp3の音楽ファイルをドラッグするだけで波形が現れます。プロが演奏した曲と自分が普段している練習曲を並べて見ることができます。目で音を確認できるという、素晴らしい発想です。

もちろん曲が違うので全体の波形は違います。しかし1音1音の波形を見ると形が違います。プロの波形はどの音もほぼ同じ形をしています。大きさも音の強弱はありますが相似形になっています。
一方、私の波形は統一感がありません。プロの波形に近づけば良いのか?。音を構成する要素は何なのか?。それがこのAudacity でわかるのか、まだ研究の余地がありそうです。
それはさておき、皆さんも一度やってみられてはいかがでしょうか。注意としては波形を見て落ち込まないことです。「百聞は一見にしかず」ということわざがあります。聞くより見た方が100倍頭に残るからです。
プロはさすがプロだなと崇める。自分も近づきたいなと、波形を見ながらモチベーションを高めていく。そしてこうして音楽をデジタルで見れる時代になったことに感謝であります。
まとめ
吹部の若い頃と、今(シニア)では考え方や物の捉え方が変わっています。それは当然と言えば、当然です。 過去の振り返りと、これからの自分の考えに変化があることに気づかされます。固い話はこれまで。。。
ホルンを吹いているこの瞬間が一番楽しいと思えれば、あなたは死ぬまで吹き続けるでしょう。
「今ここ!」
あなたが今できることは何でしょう。考えてみよう。
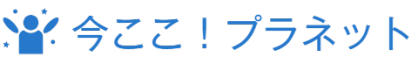




“ホルン練習 自律的思考 10選” に対して1件のコメントがあります。